2018年夏 読書本ベスト5
カテゴリー:

■脳は回復する(鈴木大介、2018、新潮新書)
■困ってる人(大野更紗、2011、ポプラ社)
■僕の妻はエイリアン(泉流星、2008、新潮文庫)
■されど愛しきお妻様(鈴木大介、2018、講談社)
■聖の青春(大崎善生、2002、講談社)
===================================
脳は回復する(鈴木大介、2018、新潮新書)
===================================
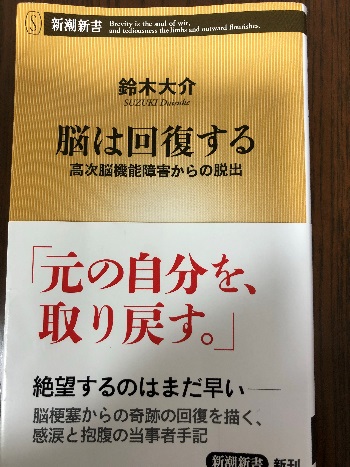
筆者は41歳で脳梗塞を発症した。その後リハビリを重ね、日常生活に復帰したが、そこで彼を待っていたのは「高次脳機能障害」の世界だった。小銭を数えることができない、女性の胸から視線を外すことができない、人混みを歩くことができない、会話ができない、イライラ感から抜け出すことができない。「高次脳機能障害」とは、主に脳卒中や事故などによる脳外傷を原因として、脳神経細胞が一部壊死してしまった結果起きる障害で、身体の麻痺などとは別に、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知機能全般や情緒面などに不具合が起きることを言う。あらゆることが号泣を伴う感情失禁が筆者をさいなみ続けた。言語聴覚療法のリハビリの先生から「泣くこともリハビリ」という金言をもらい、その先生は「その涙は、人の脳の持つ感動的な自己再生の機能なのだ」と言った。脳の感情を抑制する部位が壊れているならば、涙を流し、その程度をコントロールすることは、新たな抑制の神経ネットワークの構築につながる。その脳は再生に向けて立ち上がっているのだと。当時の筆者は、複雑な内容を伝える会話が、なにより相手の顔が見えない電話を介してのやり取りが、難しかった。携帯電話にかかってきた仕事の連絡や家族からの連絡で、何度もパニックを起こして相手が何を言っているのか分からなくなり、電話を切ることを繰り返していた。発病前に当たり前のようにやれたことの、何もかもがまともにできない。できないならまだしも、その一つ一つにいちいち死にたくなるような苦しさがついて回る。具体的に退院後にこんな苦しさに悶えることになるとは、診断書にも医師の説明にもなかった。
筆者は、発症後4か月から、自身がどんなことが出来なくなり、どんなシーンで苦しさを感じているのかの自己観察と、その理由を考察する作業に入った。そして、脳梗塞後に残った障害として、「注意障害」、「情緒の脱抑制」、「作業記憶の低下」、「脳の情報処理速度の低下」、そしてこれらが絡み合った結果として、「遂行機能障害」、「離人症」、「心因性失語」、いくつかの種類の「パニック」がおこっていた。
===================================
困ってる人(大野更紗、2011、ポプラ社)
===================================
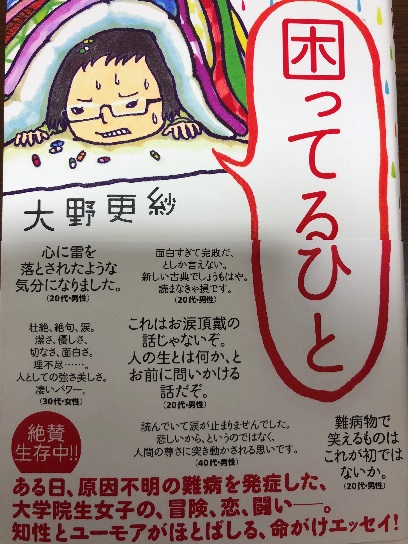
筋膜炎脂肪織炎症候群と皮膚筋炎という難病を併発した26歳大学院生女子の書いた本である。非常に希な疾患であり、普通の医療機関で診断することなど到底出来ない疾患なので、38℃以上の発熱、痛み、全身に力が入らない、関節が曲がらないなどという状態でありながら、病院を転々としたが「安静にしていれば、よくなります」と診断はつかない。このときの身体の状態は、手は脂肪組織の下までえぐれている潰瘍だらけ。手足はしこりだらけ。皮膚はただれ、口の中も炎症だらけ。眼はは涙が出ず、全身の関節は、もはや、ほとんど動かなかった。髪はすっかり抜けて、頭の地肌が露出していた。そして、発病から一年が経過した、秋のある日、「辛かったね、今までよく我慢したね。もう安心して大丈夫ですよ。必ずよくします」と敬愛すべき名医、命の恩人と出会う。そして、その後1か月間の怒涛の検査。診断が確定しステロイド療法を開始したが、副交感神経が暴走し、その苦しさにセレネースの注射を頻回に要求し、「閉じ込め症候群」状態となった。このため治療方法を変更しステロイドを少量から増量していった。それから「特定疾患」、難病医療等助成制度の申請などの手続き、さらには自立、退院に向けての毎日。それから始まる患者同士の交流。その一方で、重度の抑うつ、鬱のどん底へ落ちようとしていた。「ソーシャルワーカー室」に通い、高額療養費払い戻し制度、難病医療費等助成制度、身体障害者手帳の申請、さまざまな制度があることをここで知り、確認し、丁寧に対応してもらっていたのも束の間、「とにかく、退院して在宅に切り替える道を探るしかないんじゃないですか」と対応が変わった。さらに、大学のゼミの友人、先輩、先生、ビルマ関係の知人、高校時代の友達、とにかく、「誰か助けて」と言い続けた。そして友人たちの「厚意」「親切」をまるで当然のことのように、自然に期待し、受け取るようになっていった。その結果、お見舞いに来てくれる友人たちの表情が、暗く切ないものに変化していった。そんな中、何時間も話を聞いてくれる優しい男性と出会い、お互いに難病患者同士で「デート」した。そして一瞬にして、生存本能が息を吹き返した。書類に埋もれ、お役所窓口を巡回し手続きに動き回った。しかしついに、病院の外で生きていくために自力で通院できる「おうち」を確保し、難病女子が一人で生活を始めるまでの物語である。
短い期間ではあるが、人生を一転させる出来事が起こった。これは、健康な医療者側からすれば、外来を受診し、入院治療を受けている患者さんの日常的なことかもしれない。しかし患者さんにとっては、それまで生きてきた中で全く予想もしなかったことが次から次に現れるわけである。その実際を、若き女子が何を見て、どの様に感じ、何を考え、どの様にして生き抜いていくのか、ということを、この本を通じてわれわれは経験することができる。医療者として、患者さんが悲しい気持ちにならないよう、不快な気持ちで検査や入院生活を送ることがないよう、考えさせられた。
===================================
僕の妻はエイリアン(泉流星、2008、新潮文庫)
===================================

筆者は、幼い頃から周囲との不可解な違和感に悩み、たびたび海外へ脱出しては世界を歩いたという。英語で思考し会話するとき、自分の性格が日本語のときとは微妙に変化することに気づき、言葉の面白さに魅せられ、大学で言語学を学んだ。この本では日常生活の中で「高機能自閉症」、「アスペルガー症候群」を発症した患者さんが、どの様に暮らしているのか、何を考えているのか、その患者さんに付き添う人は何に注意して何をしてあげればよいのか、ということをわれわれに教えてくれる。
自閉症スペクトラム(広汎性発達障害)の特徴であるが、そのような人を異常といえるのかどうか、とても悩ましい。なぜならその特徴にあるように、いくつかの点で一般よりも優れた能力を発揮するからである。筆者も書いているように、この障害はいくつかの能力がデコボコでアンバランスなところに問題がある。お互いに良い関係を保つためには、足りないところをサポートするよう心がける。そして、なるべく日々のスケジュールを一定にし、急な予定変更を避け、話す場合にはその準備の時間を与えるようにする。そして何かに集中しているときは、邪魔をしないようにしよう。パニックにならないように、苦しい気持ちにならないように配慮することが大切である。
===================================
されど愛しきお妻様(鈴木大介、2018、講談社)
===================================

大人の発達障害である女性と同棲生活を営み結婚し、その苦労の中で彼女が悪性の脳腫瘍で倒れ、その後彼も脳梗塞で倒れて高次元脳機能障害を抱えることになる。しかし2人が病気で倒れ、それを介護した経験の中で、お互いがわかり合い、お互いに助け合う夫婦生活を確立していった。
その無謀ともいえる結婚生活を続けた末に、彼が脳梗塞で倒れ高次脳機能障害者となってから、話は急展開する。それまで精神的DVで彼女を傷つけてきた彼が、彼女から介護され、思い通りに考え動くこともできなかった彼女の障害を理解し、自分に対する彼女の優しさと思いやりをしみじみと感じて、変わっていく。彼自身が発病前から抱えていた問題(ある意味で異常な性癖)を変えていった。そして、彼が抱えることになった様々な不自由が、彼女の抱えてきた苦しさへの理解につながっていった。彼女は言った「ようやくあたしの気持ちがわかったか」と。
自分で自分をコントロールできないというのは、とても苦しいことだ。とにかく心がざわついて窒息感があって辛くて耐えられない状態になる。その苦しさから逃れる方法は、ただひとつ背中を撫でてもらうことだったという。その辛い状況をわれわれは少しでもわかるようにしなければならない。
===================================
聖の青春(大崎善生、2002、講談社)
===================================
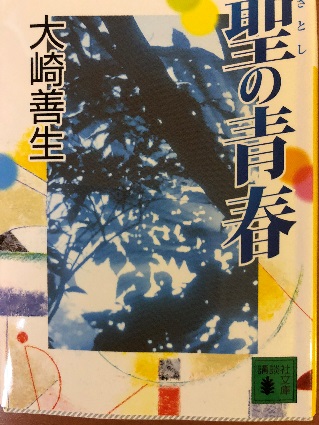
5歳の時に重い腎臓の病、ネフローゼ症候群を発症した村山聖。その病床で将棋と出会い、一生を将棋に捧げた人生。その人生は29年と短く、ただひたすら将棋会名人への道を夢見て努力した。
聖は、6歳になると、夢中で本を読むようになった。本を読むスピードは桁違いに速かった。何しろ病院のベッドの上で膨大な時間があった。そこに父親が将棋を教えた。もっともっと知りたい、自分の心をむずむずさせる将棋というものの正体はいったい何なのだろうかと聖は思い、それを少しでも知るために自分にできることはとりあえず本を読むしかないと直感した。小学1年生が読むにはあまりにもそれは難しい本だった。漢字にしても言い回し一つにしても格調が高く、とても子供の手に負えるような代物ではなかった。しかし、聖は白いシーツの上でむさぼるように読み続けた。初心者向けの将棋の単行本を何冊も読破した聖は、小学2年生の秋ごろに「将棋世界」という専門の月刊誌と出会う。そこには聖にとって知りたい情報、歯ごたえのある詰将棋や次の一手の問題、定跡の知識などありとあらゆるものが詰まっていた。「将棋世界」に没頭し、そして相手を見つけては誰彼かまわず将棋を指すそんな毎日が続いた。毎日、何時間もかけて聖は「将棋世界」の詰将棋を解きそして昇段コースの問題に取り組み、懸賞の問題には欠かさず応募した。病院のベッドの上で誰に教えてもらうわけでもなく、聖は本だけを羅針盤にしてめきめきと将棋の腕を上げていった。
聖は師匠である森とアパートで同居生活を始めた。二人とも大の風呂嫌いで顔も洗わないし歯も滅多に磨かない。師匠も弟子も、髪の毛も髭も伸び放題だった。とにかく二人とも、そういう日常的な身だしなみにまったく興味がなかった。聖は爪を切るのも嫌がった。
奨励会での対局の後は必ず体調を崩し、2、3日は病院のベッドで身動きがとれなくなった。聖は24時間何もせず、じっと目を閉じて自分の体の中に活力が蘇ってくるのをひたすら待ち続けた。少し元気が出てくると、本を読んだ。師匠の本棚で出会って以来、推理小説とコミックの面白さに目覚めていた。エラリー・クィーンばかりを20冊立て続けに読み、そして次はアガサ・クリスティに移る、そういうがむしゃらな読み方だった。コミックはなぜか少女マンガだった。少年少女たちの学校を舞台に繰り広げられる、他愛なくそして穢れのない恋愛ものが特に好きだった。ふわふわとした綿菓子のような青春像に聖の胸はわけもなくときめくのだった。
その後プロ棋士としての道を歩んでいくわけであるが、前述した病気との闘いと唯一のめり込んでいった将棋に没頭する日々の生活の中で聖という人間像が形成されていった。それは非常にアンバランスな能力を育て、自閉症スペクトラム障害であったと考えられる。他の世間一般の人々と交わることのない、そして多くの世の中の慣習に従わない、彼一人の世界の中で生活し、しかし将棋を指す能力は研ぎ澄まされていった。大病を患い、その短い人生を将棋の追及に捧げたことで、彼独自の世界を生き抜いた、唯一無二の一生だったのではないだろうか。

